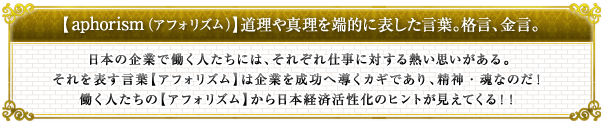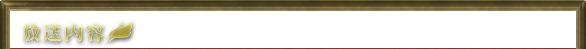― ライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社 ―
― ライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社 ―
家族葬をはじめとする小規模な葬儀サービスを展開するライフアンドデザイン・グループ西日本。そこには、変化してゆく葬儀のスタイルに対応して家族の想いに応えるプロフェッショナル達がいます。
遠方から大人数を招いて長時間にわたって執り行う葬儀から、故人をよく知る身近な人たちで送る小さな葬儀へと世の中の需要が変わる一方、故人にとってはたった一度の葬儀、送る遺族にとっても不手際は許されない大切なセレモニーであることには変わりがありません。そんな遺族の気持ちに寄り添ったお別れの場を提供するべく、創意工夫と思いやりの心をもって日々奮闘する従業員たち、そんな現場で働くスタッフたちが心に抱くアフォリズムとは・・・
【第1話】2021年9月13日(月)24:24〜
時代のニーズに対応するにはスピード感が大切
 マーケティング推進室 室長
マーケティング推進室 室長
石井寛彦さん 工事の内容まで細かく打ち合わせ
工事の内容まで細かく打ち合わせ 工事の管理から最終チェックまで
工事の管理から最終チェックまで 求められるのは生活圏内にある
求められるのは生活圏内にある
コンパクトなホール 立地調査から竣工まで、
立地調査から竣工まで、
ニーズに応じたスピード感が大切
2021年8月に大阪府堺市に完成した、ライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社の全国113ヵ所目となる家族葬ホール。工事を管理し、最終チェックを行うのは新規出店の担当責任者の石井さん。ライフアンドデザイン・グループ西日本の家族葬ホールは1日1組の貸し切りを基本とする小さなお葬式の会場。「一般的なコンビニよりも1サイズ〜2サイズ小さい会場で、気の置けない皆様だけでお見送りができることを評価していただいています」と言います。新しいホールをどこに建てるか、立地を検討するのも石井さんの仕事です。遠方から大勢の会葬者を招く葬儀よりも、故人の身近な人だけで送り出す小さくて低価格な葬儀が主流になりつつある今、必要とされるのは生活圏内にあるコンパクトなホールです。「1日1組がコンセプトですから、同じ日に同じエリアで2組の葬儀はできません。なので、隣接した生活圏に土地と建物をいち早く確保することが重要です」現にそれを求めている人がいるのならそれに応えるサービスを提供したい。
「時代のニーズに対応するにはスピード感が大切」そう心に刻んで仕事をしている石井さん。「オープンした後、こちらの会館を地域の皆様にたくさん使っていただけたことが分かった時が一番うれしいです」
ニーズに全力で応えるプロフェッショナルがいます。
【第2話】2021年9月14日(火)24:24〜
会社に自信を、仕事に誇りを持つことがお客様の安心感に繋がる
本社内のオペレーションセンターで葬儀の依頼をはじめ様々な問い合わせに対応している川端さん。センターは24時間対応、1日におよそ300件の電話がかかってくると言います。「こちらからは必要な情報だけをお伺いして、お客様がお話されたい内容があれば真摯にお聞きする、とにかくお客様の心の負担にならないよう心がけています」。最近では葬儀の依頼だけではなく“終活”の一環として事前に電話してくる方も多く、中には余命宣告をされた本人からの相談もあるといいます。「大きな不安を抱いて電話を掛けてくる人がほとんどです。まずは安心感を持ってもらえるような対応を心掛けています」。川端さん自身も5年間、現場で葬祭ディレクターをしていた経験から「当社にご依頼いただければ絶対に満足していただける」という自信があると言います。「会社に自信を持つこと、仕事に誇りを持つことがお客様の安心感に繋がっていると思っています」。社内では個別の問い合わせ情報はデータ化して全スタッフで共有しているといいます。「次にお問い合わせがあった際に、たとえ別のスタッフが電話に出たとしても情報を見て適切な対応をすることができ、お客様の安心感に繋がっていると思います」。
不安を安心感に変えるプロフェッショナルがいます。
 オペレーションセンター課長
オペレーションセンター課長
川端勇気さん 24時間対応の
24時間対応の
オペレーションセンター 不安を抱えて
不安を抱えて
電話してくる人がほとんど 問い合わせ情報はデータ化して共有
問い合わせ情報はデータ化して共有 不安を安心感に変える
不安を安心感に変える 会社に自信を、仕事に誇りを
会社に自信を、仕事に誇りを
【第3話】2021年9月15日(水)24:34〜
「自分自身ができているか」を意識する
 セレモニーチーム副主任
セレモニーチーム副主任
福井博乃さん 葬祭スタッフの研修や育成を担当
葬祭スタッフの研修や育成を担当 葬祭スタッフの仕事は
葬祭スタッフの仕事は
備品のチェックから・・・ 葬儀の打ち合わせまで多岐にわたる
葬儀の打ち合わせまで多岐にわたる 研修したスタッフが成長して
研修したスタッフが成長して
独り立ちした姿を見て身が引き締まる 自分自身ができているかを
自分自身ができているかを
意識しながらの指導
ホールに配置される葬儀スタッフの研修や育成を担当する福井さん。スタッフの仕事は、葬儀を滞りなく行うための準備や備品の管理、顧客対応から死亡診断書の代行手続きまで多岐にわたります。「私が研修を受け持つスタッフの多くは未経験の人で、まずはマニュアルを使ってしっかり座学研修を行うのですが、そのあとは早い段階で現場に入ってもらって働きながら仕事を覚えていってもらうようにしています」。そんな福井さんは、研修を終えたスタッフが現場で何か問題を抱えていないか、各地のホールに足を運びフォローを欠かしません。
スタッフを育成する上で大切にしていることは?の問いに「間違いを注意する場面もありますが、自分ができていないと説得力に欠けます。“自分自身はちゃんとできているか?”常に意識するようにしています」「私が面接して研修したスタッフが独り立ちしてやりがいを持って成長している姿を見ると嬉しく思うと同時に、私も自身を見つめ直しながら負けずに成長していかなければと思います」と目を細める福井さん。
優秀な人材を育成するプロフェッショナルがいます。
【第4話】2021年9月16日(木)24:34〜
概念にとらわれない 革新的なサービスを提供
葬祭事業の責任者角野さんはマーケティング業務も担当しています。インターネットの普及とともにいくつもの葬儀社さんを比較検討される方が増えてきたことを日々実感していると言います。そのため価格だけではない他社との違いを打ち出すために、葬儀のない時にはイベントを開催するなど、地域に溶け込み認知度を上げるための新たな取り組みを積極的に行っています。「最初の頃は、葬儀社がこんなことやっていいの?みたいな反応はありましたけれど、まずは会社を知っていただく、親しみを持っていただくということに重点を置いてやっています。」もう一つ、角野さんが重視しているのが、家族葬だからこその遺族への細やかな提案です。「お別れの時間をどう過ごすのか、例えば、最後のお別れの場で故人が大好きだったお食事を一緒にとるとか。儀式の枠内では処理しきれない極めて個人的・家族的な想いなどを汲んで、後悔の無いように様々な提案をさせていただいています。自分たちの家族を見送るとしたら、という視点だけは忘れずに概念にとらわれない革新的なサービスを提供していきたい」と角野さん。「葬儀はこうじゃなきゃいけない、とかは私の中ではどんどん無くしていきたい。お客様のニーズにマッチした革新的なサービスは続けていかないと、この業界自体も変わりませんし。」
エンディング業界に革新をもたらそうとする、プロフェッショナルたちがいました。
 事業推進グループ 執行役員
事業推進グループ 執行役員
角野拓人さん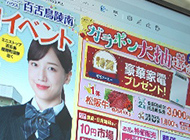 認知度と親しみを
認知度と親しみを
持ってもらうためのイベントも 葬儀社がやってもいいのか
葬儀社がやってもいいのか
議論はあった 通常の葬儀の枠にとらわれない
通常の葬儀の枠にとらわれない
細やかな提案 「葬儀はこうじゃなきゃいけない」は
「葬儀はこうじゃなきゃいけない」は
無くしていきたい