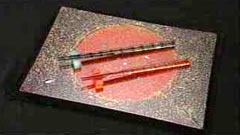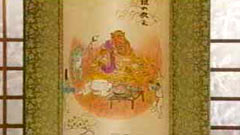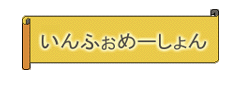| |
| 若狭を彩る伝統の技(小浜市) |
放送 9月4日(月) |
|
大陸文化が奈良や京の都へ伝わる中継基地であった小浜には、今なお磨かれた技と華やかさで人びとを魅了する数々の伝統工芸品がある。また、北前船の寄港地でもあった小浜は交易の町としても栄えた。こうした文物を通じて京都とのつながりが深く、小浜の町には京文化が根づいている。
そのひとつがかつての花街の「三丁町」。柳町、漁師町、寺町を総称して三丁町と呼んだとか、町の長さが3丁(約330m)あったので三丁町と呼んだとか言われている。三丁町の幅3mほどの狭い通りには紅殻格子の料亭が軒を並べ、家の中からは三味線の音が聞こえ、通りでは粋な着物姿の芸妓に出会うこともある。芸妓の言葉も「おいでやす」と京言葉。
|
 |
|
(写真は 御食国若狭おばま食文化館)
|
|
|

|
大陸文化の中継地だった小浜には、匠たちがその技を積み重ねてきた伝統工芸がある。若狭めのう細工、若狭漆器、若狭塗箸、若狭粘土瓦、若狭和紙などで、大陸文化の香りと華やかさに彩られた逸品が多い。
若狭めのう細工は大陸からの渡来人の玉造りの技法を、享保年間(1716〜36)に高山喜兵衛と言う人が、丸玉製造の技を修得、この技術を生かしてめのう細工始めたのが今に伝わり、彫刻、置物、アクセサリーなどが生み出されている。めのう原石に熱を加えることによって、石の中の鉄分やクロームが酸化してめのう独特の色を出す。これを細工して置き物や装身具、アクセサリーなどに仕上げる。原石からの発色、造形には職人の長年の技が工芸品の善し悪しを左右する。最盛期には約300人いた職人も現在は50人ほどになった。
|
|
(写真は 若狭めのう細工)
|
|
|
若狭塗の漆器は高級品として珍重されている。幕末の万延元年(1860)皇女・和宮が徳川家へ降嫁の際、若狭塗のタンスが献上されたとことからもその品質の良さがうかがえる。
若狭塗は江戸時代初めの慶長年間(1596〜1615)に、小浜藩の御用塗師・松浦三十郎が中国漆器にヒントを得てその技法を編み出したのが始まり。その特徴は貝殻や卵殻、金箔、銀箔、松葉、桧葉などの上に漆を何度も塗り重ね、石や炭、砥粉(とのこ)などで丹念に研ぎ出す「研ぎ出し技法」にある。完成までに数ヵ月かかり、その重厚な風格は若狭塗独特のものである。同じ技法で作られる若狭塗箸は全国生産の8割を占める特産品である。「御食国(みけつくに)若狭おばま食文化館」では、めのう細工や若狭塗の体験工房があり、「箸のふるさと館」には約3000種類の箸が展示されている。
|
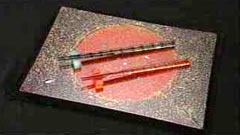 |
|
(写真は 若狭塗箸)
|
|
|
|