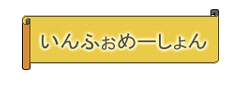|
|
|
月〜金曜日 18時54分〜19時00分 |
|
|
|
奈良・吉野町 万葉の吉野 |
|
万葉集4500余首のうち吉野を詠んだ歌は100余首あり、明日香、奈良に次いで多い。しかし、吉野山の桜を詠んだ歌は一首もなく、吉野山が桜の名所となったのは、平安時代に西行が吉野山の桜を詠んだ以後のことになる。万葉歌に詠まれた吉野は雪の名所、そして吉野川の激流や山を見ての感動であった。のどかな飛鳥の自然と比べ、吉野の山や川の険しさ、奥深さ、神秘さが万葉人たちの心を揺さぶったのであろう。 |
|
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
大海人皇子は周囲を山に囲まれている吉野は攻めることが難しく、戦略上から身をひそめるには適した土地として選んだ。後に後醍醐天皇や源義経らも吉野に逃れており、吉野の里人たちには追われの身の人たちを暖かく迎え、匿まってやる優しい心があったのだろう。 |
 |
|||
|
(写真は 桜木神社) |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
吉野の地に強い思いを寄せていた天武天皇は、後に持統天皇となった鵜野(うの)皇后としばしば吉野を訪れている。その吉野宮(吉野離宮)があったのが宮滝とされている。宮滝は斉明天皇も吉野宮を造営しており、奈良時代に入ってからは聖武天皇が吉野離宮を造営している。 |
 |
|||
|
(写真は 吉野宮復元模型) |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
吉野離宮があった宮滝から吉野川沿いに上流へ遡ったところの吉野町国栖に、天武天皇を祀る浄見原(きよみはら)神社がある。この神社で毎年、旧暦の正月14日に古式ゆかしく国栖奏(くずそう)の舞が舞われる。 |
 |
|||
|
(写真は 常滑) |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
象川をはじめ吉野の水を司る神を祀っているのが、吉野山上千本に鎮座する吉野水分神社。主神は天水分(あめのみくまり)大神で、古くから農耕の神として信仰されてきた。三つの社殿を一棟とした本殿と拝殿、幣殿(いずれも国・重文)、楼門が回廊で結ばれた境内の空間は荘厳な雰囲気の神域。本殿に祀られている秘神・玉依姫命(たまよりひめのみこと)像は鎌倉時代の神像の代表作で国宝に指定されている。 |
 |
|||
|
(写真は 象の小川) |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
さらに「ぬばたまの 夜のふけゆけば 久木(ひさぎ)生(お)ふる 清き川原に 千鳥しば鳴く」と、こちらも静寂を題材に「夜が更けてゆくと、久木の繁る清らかな川原に千鳥が絶え間なく鳴いている」と静寂の中での孤独感を詠んでいる。 |
 |
|||
|
(写真は 象山) |
||||
|
|
||||
|
|
||||