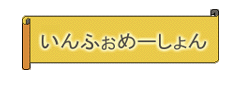| |
| 名建築に憩う・旧西尾家住宅 |
放送 5月15日(火) | |
旧西尾家住宅は約4500平方mの敷地内に、数寄屋造りの主屋のほかに蔵、離れ、茶室、庭園などが配され、重厚な旧仙洞御料庄屋の雰囲気を今に伝えている。現在の主屋は明治28年(1895)に11代当主・西尾與右衛門が建て替えた。この11代当主は書、漢学、詩の道に秀でていたほか、茶道の薮内流の奥義を極めた文化人であり、風流人であった。こうした人柄と素養が旧西尾家住宅の造りの随所に現れている。
欄間や長押(なげし)に取りつけられた水仙の釘隠しは桂離宮と同じデザイン、ほかの釘隠しも家紋や桔梗、柏の葉をデザインするなど、釘隠しひとつにも凝り、茶室付きの広間、暖炉付きの部屋など最新で斬新なアイデアが取り入れられている。
|
 |
|
(写真は ビリヤード室)
| |
|

|
大正15年(1926)に建てられた離れは、11代当主の隠居所として建てられた。設計は当時、関西の近代建築界の第一人者であった武田五一で、外観は主屋や茶室と調和した和風ながら、内部は洋室棟と和室棟が渡り廊下でつながれている。
洋室棟にはビリヤード室と数寄屋造り風のサンルーム付の応接室があり、出窓やサンルームと応接室の仕切りの欄間には、モダンなデザインとアールヌーボー風のステンドグラスがしつらえられ、華やいだ雰囲気を感じさせる。竹田は他の建築家に先駆けて取り入れた和洋折衷技法のデザインをこの離れに試みている。和室棟と洋室棟をつなぐ渡り廊下の天井は、竹と桜の皮つき丸太の木を並べた船底天井になっている。
|
|
(写真は 茶室 積翠庵)
| |
|
庭園の木立の中にある茶室「積翠庵」では、周囲の緑を愛でながらお茶が点じられる。この茶室は薮内流10代家元・休々斎の指導で明治26年(1893)に建てられたもので、大工も薮内家に出入りする大工が当たった。
積翠庵は薮内家を代表する名席「燕庵」と「雲脚席」を模して造られている。燕庵を模して造ることが許されるのは、薮内流皆伝を授かった者だけで、11代当主がいかに薮内流の茶の道に通じていたかを物語っている。
屋敷内の庭園も休々斎と薮内流9代家元の次男・薮内節庵の合作で作庭され、庭園内のあちこちに茶人らしいデザインがうかがえる。
|
 |
|
(写真は 雲脚席) |
|
|
|