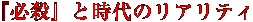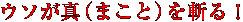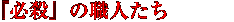山内久司、仲川利久……『必殺』の歴史は、名物プロデューサーたちが作り上げてきた歴史といっても過言ではない。彼らの後を継いで新しい『必殺』を手がけているのが、森山浩一プロデューサーだ。『必殺仕事人2007』で15年ぶりに『必殺』をよみがえらせ、『必殺仕事人2009』では連続ドラマへと発展させた。『必殺』復活の立役者にして、『必殺』の看板を背負う男が、『必殺』の醍醐味を語り尽くす。

ぶっちゃけた感想を言うと、時代にすごく左右されると感じました。新春スペシャルが終わって、第1話から第3話のとき、世の中が急激に冷え込みましたよね。そうすると、見る側の気分もがらりと変わるんです。それは痛感しました。庶民から見たら手の届かないような悪党が、闇でいろいろと画策するのを、仕事人が恨みを背負って倒す――これが『必殺』の基本的な構造ですが、庶民と巨悪との距離感があまりにも大きくなり過ぎると、「そんな話、絵空事じゃん、もういいよ」というふうに感じられてしまう。これだけ世の中が冷え込んでくると、そういう危険があるんですよ。
やっぱり『必殺』はテレビなんだなって思いましたね。作品だったら、それは時代がどうあろうが、そんなに影響されない。でも、テレビは見る側の気分によってずいぶん変わるから、時代の気分に沿わないとダメなんですよ。だから、僕らもちゃんと地に足つけて、しっかり時代と向き合ってやらないといけないと思っています。そうじゃないと、自分の番組の自己パロディみたいになっちゃいますから。後期の『必殺』はあえてマンネリを目指した時期もありましたが、今とは時代背景が違います。当時は、庶民の手が届かない悪党を倒すという『必殺』の方程式が、リアリティ抜きで成立可能だった。でも、今はもっと時代がヒリヒリしてるから、その方程式にリアリティがなければドラマは成立しないんですよ。
今のご時世を見てると、金とか、暮らしとか、職だとか、昔はテーマにならなかったようなことがテーマになってくるんです。社会の上層でお金をいやというほど儲けてる人の話よりも、「オレはこんなに一生懸命やってるのに、なんで食えないんだ」っていう話ですよね。たとえば、第6話の伊勢崎藤五郎のように、真面目に生きてきたんだけど、ふと魔がさす。で、悪い縁(えにし)に捕まって、そこから抜けられなくなってしまう。そういう話の方がリアリティを感じられるんですよ。昔は悪が大きければ大きいほどいいってところがあったと思うんですけど、今は庶民のリアリティが大事なんです。でも、ちゃんとやれば響くんだなあっていう実感もありますし、作っていて面白いですね。

やっぱり連続でやると、スペシャルだけではわからなかったことがいっぱい見えてきますね。ちょっと前までは、『必殺』は時代劇の仮面をかぶった現代劇だと、あっさり割り切ってやってたんです。でも、最近感じるのは、時代劇って意外とファンキーだなって(笑)。時代劇ってワンカット、ワンカットが全部作り物なんですよ。ようするに、全部ウソ(笑)。
たとえば、源太が舟に乗ってるシーンを撮りますよね。まず、舟に乗って悪人のところに近づくカットを本物の池で撮っていく。それが次のカットでは、源太の乗った舟が、今度はオープンセットのレールの上を走ってる。それを助監督さんが一生懸命引っぱってるわけですよ。ウソといえばウソですけど、そうしないとこのシーンは撮れないんです。まあ、そもそも源太の殺し技自体がウソじゃないですか(笑)。あのウソをどう作るか、ウソをウソのように見せずにどうやって成立させるか。それが『必殺』の美学なんですよね。ウソなんだけれども、そのウソが最終的に真(まこと)を斬る。
テレビって、派遣切りだとかGDPが下がったとか、いろいろと報道しますよね。でも、見る側からすれば、「イヤな時代だな」という鬱憤ばかりが澱(おり)のように溜まっていくだけで、それを解消する手段がテレビにはないんですよ。『必殺』は、そこを斬っちゃうわけです。これ、現代劇でやったらテロでしょう?みたいなやり方でね(笑)。警視総監なんて、もう何回殺されてることか(笑)。これは、フィクションの時代劇だからできること。単に時代劇の仮面をかぶった現代劇というだけじゃなくて、テレビからもらった欲求不満をテレビの中で解消できる。『必殺』はすごいシステムですよ。

『必殺』のスタッフは、ほんとに面白い。スタッフは京都の人が多いんですが、京都って町自体がいわゆる分業の町なんです。着物を一着作るにしても、生地があって染屋があって、全部が分業なんですよね。それぞれの仕事は別々だから、自分が作ったものを次の人間がどうするかはわからないんだけども、できあがるもののトータルイメージはみんながそれぞれ持ってるんですよ。
撮影所も同じです。照明部、録音部、撮影部……それぞれの担当にイメージがあって、芝居に対しても口を出す。たとえば、録音部が「このセリフおかしいな。こんな言い方するか?」って言い出すなんて、ふつうは絶対にありませんよ。時代劇だから現代劇の用語は使わないというのもありますが、「『あんた』、『あんた』ときて、なんで急にここで『おまえ』になんねん」とか言ったりね。そんなことまで全部指摘するんです。それが録音部の職人として職務をまっとうするということなんですよ。だから、俳優さんに対しても、「お前ら、俳優部だから、ちゃんと芝居せえよ」って言うわけです。僕ら、プロデューサーからすると、「おいおいおい、そんなふうに言っちゃって大丈夫か」って思うときもあるんですけど(笑)。でも、それは『必殺』のスタッフだから大丈夫なんです。何十年にもわたって『必殺』を撮り続けてきたから信頼されてるし、尊敬もされてますからね。そういう人たちと仕事できるっていうのは、ものすごく面白いですよ。(後編へ続く)