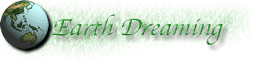
|
3月2日 ゲスト:漫画家矢口高雄さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 手塚「矢口先生の代表作“釣りキチ三平”が平成版として復活しましたが、あえてこれを復活された思いをお聞かせ下さい」矢口「昭和48〜58年の10年間連載された物なんですが、その最終回を描くに当たってもう三平は書かないと強く誓ったんです。それは昭和の時代の三平の役割というのは終わったと思ったからです。それで一昨年僕が漫画家生活30年だったので、郷里でパーティがあってその席でまた三平君に会いたいね、多くの人に言われたんです。それでその晩、昭和の三平で目指した物が平成になってどのくらい達成されたかと考えてみたんです。そうしたらちっとも良くなってないんじゃないの、と思ったんです。三平君は釣りのマンガですから、釣り場を綺麗にですとか、マナー良く、自然破壊、エコロジーと言うよなところから作品を作ってきたんです。それが現代は地球温暖化や、酸性雨と言った当時なかった問題が出てきて、学校でもいじめの問題ですとか不登校だとか、そして何よりも腹立たしいのは、若年の凶悪犯罪が増えているということ。だからこんな時代はやっぱり三平君が活躍する舞台なんだなぁ〜と思ったんです」手塚「20年ぐらいたっていますと昔の読者はお父さんお母さんになっていますね〜」矢口「平成版の第1作目を描いていたときは、今の読者がこれを受け入れてくれるだろうかとという不安感の方が大きかったんですが、いざ出版してみたら30〜40代の人に大反響だったんです。現代はスローライフとか癒し系という価値観が生まれてきました。それで考えてみると三平君にはその要素が全部入っているんだなぁ〜とつくづく思っています」 手塚「矢口先生の代表作“釣りキチ三平”が平成版として復活しましたが、あえてこれを復活された思いをお聞かせ下さい」矢口「昭和48〜58年の10年間連載された物なんですが、その最終回を描くに当たってもう三平は書かないと強く誓ったんです。それは昭和の時代の三平の役割というのは終わったと思ったからです。それで一昨年僕が漫画家生活30年だったので、郷里でパーティがあってその席でまた三平君に会いたいね、多くの人に言われたんです。それでその晩、昭和の三平で目指した物が平成になってどのくらい達成されたかと考えてみたんです。そうしたらちっとも良くなってないんじゃないの、と思ったんです。三平君は釣りのマンガですから、釣り場を綺麗にですとか、マナー良く、自然破壊、エコロジーと言うよなところから作品を作ってきたんです。それが現代は地球温暖化や、酸性雨と言った当時なかった問題が出てきて、学校でもいじめの問題ですとか不登校だとか、そして何よりも腹立たしいのは、若年の凶悪犯罪が増えているということ。だからこんな時代はやっぱり三平君が活躍する舞台なんだなぁ〜と思ったんです」手塚「20年ぐらいたっていますと昔の読者はお父さんお母さんになっていますね〜」矢口「平成版の第1作目を描いていたときは、今の読者がこれを受け入れてくれるだろうかとという不安感の方が大きかったんですが、いざ出版してみたら30〜40代の人に大反響だったんです。現代はスローライフとか癒し系という価値観が生まれてきました。それで考えてみると三平君にはその要素が全部入っているんだなぁ〜とつくづく思っています」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月9日 ゲスト:矢口高雄さん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 手塚「矢口先生は秋田の山の奥で子供時代を過ごされたということですが、自然環境も良かったんでしょうね?」矢口「自然環境が良かったとは子供の頃は思わなかったけれど、夏は見上げれば山、見渡せば山。見上げれば緑、見渡せば緑。ところが冬になると3m〜4mの雪に覆われて、見上げれば白、見渡せば白という世界になるんです。雪というのは、なんでこんな所に生まれたんだろうと思うぐらい、イヤでしたね」手塚「そのイヤな雪が溶けて緑が芽吹いてくる喜びというのは、都会にいる私達とは全然違うんでしょうね」矢口「全然違うね。土手にフキノトウがでてくると、もう嬉しくて嬉しくてね。あれは雪のない地方の人たちには味わうことが出来ないでしょうね」
手塚「矢口先生は秋田の山の奥で子供時代を過ごされたということですが、自然環境も良かったんでしょうね?」矢口「自然環境が良かったとは子供の頃は思わなかったけれど、夏は見上げれば山、見渡せば山。見上げれば緑、見渡せば緑。ところが冬になると3m〜4mの雪に覆われて、見上げれば白、見渡せば白という世界になるんです。雪というのは、なんでこんな所に生まれたんだろうと思うぐらい、イヤでしたね」手塚「そのイヤな雪が溶けて緑が芽吹いてくる喜びというのは、都会にいる私達とは全然違うんでしょうね」矢口「全然違うね。土手にフキノトウがでてくると、もう嬉しくて嬉しくてね。あれは雪のない地方の人たちには味わうことが出来ないでしょうね」矢口「手塚先生はペンネームに虫を付けるくらい昆虫が好きでしたよね。で僕は蝶マニア、蝶を追って夏中飛び回っていました。珍しい蝶を見つけると新種発見だって躍り上がって、学校の図書館の図鑑で調べてみたら、もう載っていてがっかりしたことが良くありました(笑)僕の村のあたりにはだいたい128種類ぐらい蝶がいると言われているんだけど、小学3年生から高校3年までの間にその内の96種類まで集めました。蝶は自然を観察しないと捕まえられないので、知らず知らずのうちに勉強していたんだなと思いますね」 矢口「釣りキチ三平/平成版の“天狗森の巨大魚”にも書いたんだんけれど、僕たちが子供の時には電気がきていなかったので、漆黒の闇というのをしょっちゅう体験しました。今はどんな山の中に行っても、24時間自動販売機の明かりが煌々と点いていますし、街灯もあるから漆黒の闇なんて味わうすべが無くなってるよね。真っ暗闇というのを味わうと、身体が敏感に、五感が研ぎ澄まされてきて、道ばたの石につま先が当たるとフットからだが浮くような、泳ぐように歩くんだよね。都会にいるとそういう体験が出来ないから、五感とかを眠らせたままにしているのかもしれませんね」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 手塚「都会に暮らす子供達に、矢口先生からメッセージを頂きたいのですが」矢口「僕らの頃と決定的に違うのは、自分で工夫するというのがあんまり無いように思います。僕たちの頃はお金もなかったですから、虫取り網なども自分で作りました...そういうところから創造性も身に付くと思うから、大切だと思いますね」 手塚「都会に暮らす子供達に、矢口先生からメッセージを頂きたいのですが」矢口「僕らの頃と決定的に違うのは、自分で工夫するというのがあんまり無いように思います。僕たちの頃はお金もなかったですから、虫取り網なども自分で作りました...そういうところから創造性も身に付くと思うから、大切だと思いますね」手塚「矢口先生のこれからの活動について教えてください」矢口「僕もいい年になって、そんなにマンガを書き続けられるかなと言うところにきているんだけど(笑)今僕が誇りに思っていることがひとつあるんです。それは手塚先生に勝ったよということ。手塚先生より長生きしてるよということ(笑)手塚先生や石ノ森章太郎さん、藤子F不二雄さんなどを思うとき、生涯現役でありたいなとこの年になるとつくづく考えますよね。非常に月並みかもしれないけど、身体に注意して一作一作丁寧に書いていこうと...これあんまりおもしろくないね〜」手塚「いえいえ、生きてこそですよ」矢口「まぁずっとね、釣りキチ三平に代表されるように僕の作品はバックボーンは大自然ということで、自然と人間との関わりをテーマにした作品を書いていきたいと思っています。これを貫けられたら、僕の誇りであるのかもしれないけどね」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三國清三さん | 鈴木基芳さん、湯川信矢さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る
 手塚「私の父、手塚治虫の作品との出会いをきっかけに漫画家を目指した矢口先生ですが、その辺のお話から...」矢口「小学校3年の冬休みに、村の若者がマンガが好きな僕のために“流線型事件”という手塚先生の本を買ってきてくれたんです。それを一気に読んでファンになり、大きくなったら手塚治虫のような漫画家になりたいなぁ〜と考えました。それで少ないお小遣いの中から先生の単行本を買って読んだものですね〜。でもその当時漫画家というのは独立した職業だとは誰も考えていませんでしたから、僕も踏ん切りがつかず高校を卒業して銀行マンになったんです。そこに12年勤めて、30歳になったときに少年の時の夢を実現させようと思い、銀行を辞めて上京したんです」手塚「手塚治虫と初めてあったのは?」矢口「1970年の7月にデビューして、その年の暮れに出版社が行った忘年会で、ナマ手塚治虫を見ました(笑)あと手塚先生の思いでといえば、手塚先生に叱られたことがあるんです。神戸のポートピアでサイン会があって、僕と手塚先生が行ったんです。その後宝塚の温泉に行って一泊する予定だったんです。その向かう車のなかで、手塚先生が新幹線や飛行機の中でも原稿書いて忙しいと言ったんです。それで僕は不用意にその作品は受けなければいいのに、と言ってしまったんです。そしたら僕だって受けたくないよ!!!と怒ってしまったんです(笑)で結局手塚先生は、その日は泊まらずに飛行機で帰ってしまったんです。本当に忙しいようでした」
手塚「私の父、手塚治虫の作品との出会いをきっかけに漫画家を目指した矢口先生ですが、その辺のお話から...」矢口「小学校3年の冬休みに、村の若者がマンガが好きな僕のために“流線型事件”という手塚先生の本を買ってきてくれたんです。それを一気に読んでファンになり、大きくなったら手塚治虫のような漫画家になりたいなぁ〜と考えました。それで少ないお小遣いの中から先生の単行本を買って読んだものですね〜。でもその当時漫画家というのは独立した職業だとは誰も考えていませんでしたから、僕も踏ん切りがつかず高校を卒業して銀行マンになったんです。そこに12年勤めて、30歳になったときに少年の時の夢を実現させようと思い、銀行を辞めて上京したんです」手塚「手塚治虫と初めてあったのは?」矢口「1970年の7月にデビューして、その年の暮れに出版社が行った忘年会で、ナマ手塚治虫を見ました(笑)あと手塚先生の思いでといえば、手塚先生に叱られたことがあるんです。神戸のポートピアでサイン会があって、僕と手塚先生が行ったんです。その後宝塚の温泉に行って一泊する予定だったんです。その向かう車のなかで、手塚先生が新幹線や飛行機の中でも原稿書いて忙しいと言ったんです。それで僕は不用意にその作品は受けなければいいのに、と言ってしまったんです。そしたら僕だって受けたくないよ!!!と怒ってしまったんです(笑)で結局手塚先生は、その日は泊まらずに飛行機で帰ってしまったんです。本当に忙しいようでした」