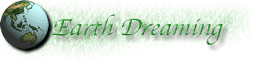
|
4月7日 ゲスト:早稲田大学理工学部教授
工学博士 高西淳夫さん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手塚「具体的にどんなロボットを作られているんですか?」高西「私自身が2足歩行のロボットを研究していますので、それを続けています。その他には下半身だけでなく、上半身や腕をつけたロボット。咀嚼出来るロボット。フルートを演奏するロボット。顔のロボット。ネズミなどの動物ロボットなどを作っています」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 手塚「ロボットの実用化というのはどの程度進んでいるのですか?」高西「一番役に立ったロボットは工場の中の、産業用ロボットですね。工場以外ではまだまだ普及していないですね。最近注目を浴びているのが医療用です」 手塚「ロボットの実用化というのはどの程度進んでいるのですか?」高西「一番役に立ったロボットは工場の中の、産業用ロボットですね。工場以外ではまだまだ普及していないですね。最近注目を浴びているのが医療用です」
手塚「自立型ロボットというのはどうなんですか?」高西「これはすごく難しいことなんです。もし家庭に入っていくとしたら、自立型、操縦型の両方を兼ね備えたロボットになると思います」手塚「今の家電みたいなものですね」高西「今の家電はロボットの概念が組み込まれています。ただ人の役に立つヒューマノイドロボットに必要なのは、コミュニケーションだと思います。これからのロボットは、学習していくロボットです。それを教えるのは人間ですよね、ですから形も人と同じ方がいいんです」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月14日 ゲスト:高西淳夫さん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 手塚「ヒューマノイド型の自律ロボットが私達の社会に入ってくると、私達も変わらなければいけなくなると思うんですが」高西「そうですね。ロボットは人と人との関係ほど強くはないですが、家電製品よりは強い関係といえるので、当然問題も起こると思います」
手塚「ヒューマノイド型の自律ロボットが私達の社会に入ってくると、私達も変わらなければいけなくなると思うんですが」高西「そうですね。ロボットは人と人との関係ほど強くはないですが、家電製品よりは強い関係といえるので、当然問題も起こると思います」手塚「例えば、家庭にロボットを入れるためには、いわゆる免許証が必要になるのですか?」高西「技術のレベルによると思います。例えば人間が間違った命令を下したときに、“それは違う” と言う判断を下せるロボットだと問題はないですが、中途半端の自立性しか持っていないロボットだと、必要だと思います」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 手塚「ロボットが家庭に入ってきたときに、法律も整備しなくてはいけないんでしょうね」高西「それはそう思います。社会システムとして考えなくてはいけないと思っています。まず一つは“免許制にする”そして“保険”。100%の安全性というのはあり得ないので、何かあったときはお金であがなうというシステムを作ることですね。 手塚「ロボットが家庭に入ってきたときに、法律も整備しなくてはいけないんでしょうね」高西「それはそう思います。社会システムとして考えなくてはいけないと思っています。まず一つは“免許制にする”そして“保険”。100%の安全性というのはあり得ないので、何かあったときはお金であがなうというシステムを作ることですね。それと私はブラックチップと呼んでいますが、ロボットが何か問題を起こしたときに、ユーザーの命令で問題を起こしたのか、ソフトの問題なのか、というのを記録するチップ。いわゆる航空機で言う、ブラックボックス的な物を組み込んだ方がいいと思っています」 手塚「先生のお話を聞いていると、アトムの話とダブってきますね」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立川町風力発電レポート2 | 坂本美雨さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る
 今週はヒューマノイドロボットの第一人者、高西淳夫先生をお招きしました。
今週はヒューマノイドロボットの第一人者、高西淳夫先生をお招きしました。