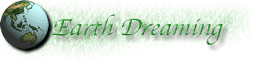
|
8月27日ゲスト: 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 安藤直人さん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手塚「安藤先生はなぜ、森林や木材に興味を持たれたのですか?」安藤「中学高時代はワンダーフォーゲルをやっていまして、山の中を歩いていたんです。それで建築は趣味だったんです。ですから建築に進んだ学生より、本を読みあさっていたんだと思います。そのうちに木と建築が結びついてきてしまって、今日に至ったわけです。特に何になりたいと思っていたわけではなかったのですが、結果的にそうなったんです」 手塚「日本の森林の現状をお教えください」安藤「日本の国土の3分の2が森林なんです。その内の4割は人工林です。森と言うと人の手の入らない山を思いがちですが、日本の山というのは戦後、植林によって大分人の手が入って今日に至っています。戦後、木を切り過ぎてしまって、植林をしたその木が育ってちょうど今使う時期になったんです。ですから今これらの木を切って、新しい木を植えないと50年後100年後、育った使える木が無くなるんです。森を守るということは使いながら、また植えながら更新していく必要があるのです。又木を育てるためには間伐をしなければいけない、そうしないとモヤシのような木ばかりなってしまいます。そしてその切った木を有効に利用することが求められています。主に住宅用材や紙として使いますが、紙の分野で国産材はほとんど使われいません。ですから日本の木は余ってしまっている、木を切らない状態にあります。ここがポイントで、これは将来に向かって難しい曲面に我々は立っているのです。地球を救う、あるいは日本の森林を救うには、日本の木を使い始めなければいけない、輸入された木は減ると思いますが、日本の木を活用することがポイントだと思います。山がモヤシのような木ばかりですと大変なことになります。台風や大雨があっても健康な木でしたら水を蓄えてくれます。又日本の飲み水は安全と言われています。これも森が蓄えているからなんです。ですから我々の大事な飲み水、生活の安全、地域の安全を山が、森が保水ということで果たしているわけです。このバランスが崩れてしまうと将来、安定的な生活が出来なくなってしまうというわけです」」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 手塚「木を切るというのは悪いイメージありますけど、必要な部分は切らないと山のために、自然のためにもよくない。又切った木は有効に利用しないといけない。それが今の日本はストップしているわけですね」安藤「木を切るのは罪悪感がありますが、もう一つ大事なのは植えるということです。今植えるということは50年後、100年後のことを考えることですから、森林の話は長い目で見て、今やるべきことをやるということです」 手塚「木を切るというのは悪いイメージありますけど、必要な部分は切らないと山のために、自然のためにもよくない。又切った木は有効に利用しないといけない。それが今の日本はストップしているわけですね」安藤「木を切るのは罪悪感がありますが、もう一つ大事なのは植えるということです。今植えるということは50年後、100年後のことを考えることですから、森林の話は長い目で見て、今やるべきことをやるということです」
手塚「今8割が輸入された木でそうですが、国産と海外の材木としての大きな違いはなんですか?」安藤「もちろん種類が違いますね。日本の木と言えば杉、檜、唐松、広葉樹もいろいろ沢山あります。ブナ、楢などそれはそれぞれ使われます。海外から来るものは最近は針葉樹です。木の悪いイメージというのは、かつて東南アジア、今はアマゾンなどの熱帯雨林を合板にして、高速道路を造るため、ビルを造るためのコンクリート用の型枠として使われました。結果、熱帯雨林の資源国の木は枯渇したんです。さらにこれは高い値段で売れたわけですから、現地で森林破壊を起こしているます。ここで大事なのは切りすぎてしまうと森林を破壊してしまう。それに対して日本の森はほったらかしですから、森林は荒廃してします。破壊と荒廃。ここを直してバラスをとっていかないと地球全体にも影響が出ます。日本は木で生活をしていました。まな板やおひつ。風呂桶など。それがいつの間にか金属やプラスティックに置き換わってしまいました。プラスティックは石油、金属は加工するのにものすごいエネルギーが必要です。エネルギーを使うということはものすごく二酸化炭素を排出するということです。木は二酸化炭素を固定して、酸素を出し、ボディは炭素の固まりです。ですから二酸化炭素を減らすには木を育てるということが大事なんです。京都議定書の日本の目標値『-6%』の内、3.9%は森林を育てることで減らせると考えています。又一度金属やプラスティックに置き換わったものを再び木に戻そうとしています。木ですから『木ーワード』として『かきくけこ』『環境、教育、暮らし、健康、心』これらはすべて木と結びついているということです」 手塚「林野庁では『木づかい運動』というのを行っていますが、これは?」安藤「本来の意味の『気遣い』ということであれば、もっと環境に、森林に気を遣ってください。そして木を使ってください、そして出来れば国産材を使ってくださいということです。国産材を使っていれば何らかの形で森林や山まで経済の循環の中に入っているということです」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月3日 ゲスト:安藤直人さん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 手塚「輸入材と国産材の見分け方はあるのですか?」安藤「あの〜、なかなか木に表示はされていませんのでね、難しいですね(笑)ただ一部の商品に国産です、ということを表す表示『3.9GREENSTYLE』というラベルがまだまだ少ないですが、
貼られています。もしそのマークの物を見つけたら是非積極的に手に取っていただきたいと思います」 手塚「輸入材と国産材の見分け方はあるのですか?」安藤「あの〜、なかなか木に表示はされていませんのでね、難しいですね(笑)ただ一部の商品に国産です、ということを表す表示『3.9GREENSTYLE』というラベルがまだまだ少ないですが、
貼られています。もしそのマークの物を見つけたら是非積極的に手に取っていただきたいと思います」
手塚「“もう一度木の良さ、木を使った物の良さを見直して使っていきましょう”という中で、最近増えてきていること、変わってきていることはありますか?」安藤「『LOHAS』という言葉がありますね。そのようなライフスタイルに変わってきていると思います。いわゆる無垢の木の家具、デザインされた家具、これは日本のものばかりではありません、世界的にみてもそうです。皆さんは日本の中で『木』と言うと、昔のおじいちゃんおばあちゃんの家に繋がりやすいのですが、実はデザインされた新しい物が沢山あります。また皆さん木は温かいと言います。木は顕微鏡で見るとストローが集まったような構造になっていますので、中に空気が入っています。ですから人間から熱を奪わないのです。金属は冷たいですね、それは熱を奪っているからです。同じ気温で人間にとって優しいのは木ということです。『にんべん』に『木』と書くと『休』という字ですよね、そういうこともあるんじゃないでしょうか」 手塚「私たち個人個人がどのくらい木材を使ったら良いかという目標値はあるのですか?」安藤「日本全体で木材の年間使用量はおよそ9千万立方メートルです。その中での2割が国産です。今、木が育っていますので、2千5百万立方メートルまで国産の木を使うことが出来ます。またそれが目標になっています。ただこれ大変な数で、よく分からない数ですよね。『木づかい運動』は徐々に徐々に一人一人が木を使っていこうということです、急激に木を使ってしまってもそれはそれでバランスを崩しますから、そのへんをお考えくださればと思います」 手塚「毎年10月を『木づかい推進月間』賭されているそうですが、今年は?」安藤「去年から始めたキャンペーンで、今年は福岡、横浜、札幌でシンポジウムを開きます。また『木づかい応援団』というのがあります。これはプロ野球のOBたち、マスターズリーグの方達で結成されています。プロ野球の日本シリーズ終わって11月からマスターズリーグが始まります。その中で『木づかい運動』のキャンペーンをやります。ですから野球を見に来ていただいて、そこでまた『木』に関心を持っていただければと思っています」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
林野庁『木づかい運動』のホームページはhttp://www.rinya.maff.go.jp/kizukai.htmlです |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冨田秀実さん、小西雅子さん | 小西雅子さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る
 手塚「安藤先生、この『農学生命科学研究科』ではどういった研究をされているのですか?」安藤「いわゆる農学部なんですが、今や生命科学分野、DNAや生命の神秘といった所まで研究範囲が及んでいますので、広い意味で生命体を扱っています。その中で我々は木材資源をいかに有効に使うかという研究をしていて、その中でもとりわけ建築材料へいかに転換して、木造建築を作るかということが、私自身のテーマの分野です」手塚「また先生は『林政審議会』特別委員を努めていらっしゃいますが、どういう会なのですか?」安藤「具体的には林業白書を作ることが主たる目的です。現状の分析、歴史的分析をふまえて、これからどうしたら良いのかということをその白書の中に盛り込んでいくお手伝いをしています」
手塚「安藤先生、この『農学生命科学研究科』ではどういった研究をされているのですか?」安藤「いわゆる農学部なんですが、今や生命科学分野、DNAや生命の神秘といった所まで研究範囲が及んでいますので、広い意味で生命体を扱っています。その中で我々は木材資源をいかに有効に使うかという研究をしていて、その中でもとりわけ建築材料へいかに転換して、木造建築を作るかということが、私自身のテーマの分野です」手塚「また先生は『林政審議会』特別委員を努めていらっしゃいますが、どういう会なのですか?」安藤「具体的には林業白書を作ることが主たる目的です。現状の分析、歴史的分析をふまえて、これからどうしたら良いのかということをその白書の中に盛り込んでいくお手伝いをしています」 手塚「私の回りで森林破壊を気にして、『マイ箸』を持ち歩く人がいたんですが、安藤先生はマイ箸と割り箸どちらを使う方が良いとお考えですか?」安藤「割り箸は使い捨てだからもったいないということで一つの象徴のように扱われました。ところが使っている実際の材料のことを言いますと、決して建築で使うような材料を箸にしているわけではありません。1本の柱を取ると、木を四角くするわけですから、回りから使えない部分が出てきます。それを箸にしているので、もったいないのではなく、有効活用しているわけです。そして今は割り箸を捨てるのではなく、回収してパルプに使っています。ですからかつて言われたもったいないというのは現状を誤認してたかなと思います。森林を守ろうということは正しいことです。ですが割り箸を使わないから森林が守れるかと言ったら、実はそうではないんです。ただ生活態度として無駄を省こうというのは正しいです。それから今、コンビニに行ってお弁当を買っても箸がついています。皆さんサービスのように感じていますが、あれもお金がかかっています。現状は中国からの輸入の箸がほとんどです。国産の木を使った箸は単価が高いからです。ですから日本の森林を守るために、むしろ国産のお箸を積極的に買っていただきたいぐらいですね」
手塚「私の回りで森林破壊を気にして、『マイ箸』を持ち歩く人がいたんですが、安藤先生はマイ箸と割り箸どちらを使う方が良いとお考えですか?」安藤「割り箸は使い捨てだからもったいないということで一つの象徴のように扱われました。ところが使っている実際の材料のことを言いますと、決して建築で使うような材料を箸にしているわけではありません。1本の柱を取ると、木を四角くするわけですから、回りから使えない部分が出てきます。それを箸にしているので、もったいないのではなく、有効活用しているわけです。そして今は割り箸を捨てるのではなく、回収してパルプに使っています。ですからかつて言われたもったいないというのは現状を誤認してたかなと思います。森林を守ろうということは正しいことです。ですが割り箸を使わないから森林が守れるかと言ったら、実はそうではないんです。ただ生活態度として無駄を省こうというのは正しいです。それから今、コンビニに行ってお弁当を買っても箸がついています。皆さんサービスのように感じていますが、あれもお金がかかっています。現状は中国からの輸入の箸がほとんどです。国産の木を使った箸は単価が高いからです。ですから日本の森林を守るために、むしろ国産のお箸を積極的に買っていただきたいぐらいですね」