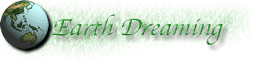
|
9月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲスト: WWFジャパン 気候変動担当オフィサー小西雅子さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手塚「今回のワールドカップは世界で最初の温室効果ガス排出量ゼロにするという目標を掲げた大会でした。これは『グリーンゴール』というコンセプトでした。これはどういったことなのでしょうか?」小西「大会を開きますと世界中から人が集まります。移動し、食事をし、照明を使います。その環境負荷を世界的に見て『ゼロ』にしようというのが『グリーンゴール』のコンセプトです。そのためにはまず省エネ。そしてどうしても出てしまうものは世界の違う地域で削減して相殺するということです。今回新しいことはそれぞれに数値目標を付けたことです。何パーセント削減というゴールを作り、それを後で評価するというやり方です。例えばゴミはスタジアム内外で20%削減しましょう、そのためにはリユースカップの導入など、細かいこと一つ一つやりました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 手塚「持ち込む物も制限されたようですね」小西「そうらしいですね。それとスポンサーが配る物も最小限に抑えられたようです。今どのくらい削減されたかを評価しています。もし今まで通りにやっていたらどうなっていたかというのと比べています。やりっ放しではなくちゃんと、誰も見てないのに評価するということは素晴らしいですね」 手塚「持ち込む物も制限されたようですね」小西「そうらしいですね。それとスポンサーが配る物も最小限に抑えられたようです。今どのくらい削減されたかを評価しています。もし今まで通りにやっていたらどうなっていたかというのと比べています。やりっ放しではなくちゃんと、誰も見てないのに評価するということは素晴らしいですね」
手塚「スタジアムで使われる電力などのエネルギーに関しては?」小西「省エネと再生可能なエネルギーを使うという目標を掲げました。12のスタジアムの電力使用量が200万〜300万kwと言われています。これは500世帯〜700世帯の1年分に相当します。照明灯などは拡散してしまう明かりを反射板で囲むことによって照明効率を上げ、照明の数を減らしました。また機器も省エネ機器に変える、屋根を太陽光発電にするなど、それぞれのスタジアムが競って対策をとっていました」 手塚「大量に使われる水に関しては?」小西「グランドの芝に散水するのが一番水を使うということで、雨水を利用する仕組みを取り入れた所もありました。またトイレ、男性用は『無水トイレ』を使用したり、効率よく水が流れるようにして、量を減らしました。新しい技術を取り入れて効率を上げています」 手塚「続いて交通ですが」小西「今回これが一番めざましかったのではないかと思います。大会開催中に排出される温室効果ガスの80%は移動する手段だと言われています。そこで主催者側が考えたのが、観戦チケットで公共交通機関が只になるようにしました。そして駐車場の値段を高くして、50%の人に公共交通機関を使ってもらおうとしました。感心したのは大会が認めたジャーナリストには国内の移動がすべて只になるパスを渡していました。これは結果が出ていまして、70%の観客が公共交通機関を利用したそうです」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月17日 ゲスト:小西雅子さん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

手塚「具体的にはインドではバイオマス調理器を導入したということですが?」小西「簡単に言いますと牛の糞なんです。まず津波の被害があった地域、1,000家庭に牛を1頭ずつ配りました。牛がいれば牛乳をとることも出来ます。そして牛の糞からはメタンガスが発生します。その糞を集めて、メタンガスを醗酵させて電気を作るという設備を作りました。この電気で調理をするということです。またこれで重労働や、健康被害も防げます。今までは火を熾すために薪をとってきました。これは子供や女性の仕事で重労働でした。また家の中で薪を燃やすので、煙が充満します。そのガスを吸い込むことによってインドで年間40万人の女性が亡くなっていました。それらからこのプロジェクトで解放されます」 手塚「次回の南アフリカ大会も同じ仕組みですか?」小西これはちょっと違います。ゴミ処理場から出るメタンガスで電気を作ったり、近くの工場で廃棄物として出されていたおがくずを集めて電気に変えます。おがくずはそのへんに積み上げられていて、メタンガスが発生し住民の健康被害が問題になっていましたので、これも解決されます」 手塚「このドイツ大会で行った環境対策運動はワールドカップに限らず様々なスポーツイベントなどに活用して行くことが可能なでは、と思うのですが」小西「まさにおっしゃる通りで、ドイツはこれからのお手本になりたいという気持ちが多くあります。この結果は10月下旬から11月ぐらいに出ますので、それを持って11月に行われる2つの国際会議で発表されることになっています」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤直人さん | 鈴木幸一さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る

 手塚「『グリーンゴール』の中に『どうしても出てしまうものは世界の違う地域で削減して相殺する』というのがありますがこれは?」小西「これは『CDM(Clean
Development Mechanism-クリーン開発メカニズム)』という京都議定書の中の仕組みを使って行われるものです。『CDM』とは先進国が資金や技術を使って、開発途上国で排出削減のプロジェクトを行います。その結果削減出来た排出権クレジットを自分の国が削減出来たものとしてカウントすることが出来る、という仕組みです。『CDM』は今世界中で行われていますが必ずしも良いものばかりではありません。『CDM』には2つの大きな目標があります。1つは地球全体で見て温室効果ガスの削減がなされるプロジェクトであること。2つ目はその事業を行う発展途上国の人々の生活に役立つこと。つまり持続的な発展につながるプロジェクトでなければならない、ということです。しかし、今世界で多く行われている排出権プロジェクトは、冷蔵庫の冷媒に使う代替フロンを作る時に出るガスを破壊するプロジェクトです。なぜ多いかと言いますと、このガスを1トン削減すると、二酸化ガスを1万倍削減したのと同じ効果になると言われているからです。ということはこのガスを削減すると簡単に、安く、そして多くの排出権クレジットが手に入るわけです。しかしこれは発展途上国の人にとって役立つ技術ではないのです。ここに矛盾が生じます。そこで私たちWWFは良いプロジェクトが世の中に広がって欲しいと言う願いをこめて『ゴールド・スタンダード』というのを発行しています。これは省エネプロジェクトか再生可能エネルギープロジェクトで、発展途上国の人達の生活に役立つプロジェクトであるという基準を満たしているプロジェクトに贈っています。それで今回のドイツ大会はその『ゴールド・スタンダード』の中からわざわざ選んでいるのです。それは、今回のドイツ大会と、次回の南アフリカ大会で行われるプロジェクト。そして津波で苦しんだインドのプロジェクトの3つです」
手塚「『グリーンゴール』の中に『どうしても出てしまうものは世界の違う地域で削減して相殺する』というのがありますがこれは?」小西「これは『CDM(Clean
Development Mechanism-クリーン開発メカニズム)』という京都議定書の中の仕組みを使って行われるものです。『CDM』とは先進国が資金や技術を使って、開発途上国で排出削減のプロジェクトを行います。その結果削減出来た排出権クレジットを自分の国が削減出来たものとしてカウントすることが出来る、という仕組みです。『CDM』は今世界中で行われていますが必ずしも良いものばかりではありません。『CDM』には2つの大きな目標があります。1つは地球全体で見て温室効果ガスの削減がなされるプロジェクトであること。2つ目はその事業を行う発展途上国の人々の生活に役立つこと。つまり持続的な発展につながるプロジェクトでなければならない、ということです。しかし、今世界で多く行われている排出権プロジェクトは、冷蔵庫の冷媒に使う代替フロンを作る時に出るガスを破壊するプロジェクトです。なぜ多いかと言いますと、このガスを1トン削減すると、二酸化ガスを1万倍削減したのと同じ効果になると言われているからです。ということはこのガスを削減すると簡単に、安く、そして多くの排出権クレジットが手に入るわけです。しかしこれは発展途上国の人にとって役立つ技術ではないのです。ここに矛盾が生じます。そこで私たちWWFは良いプロジェクトが世の中に広がって欲しいと言う願いをこめて『ゴールド・スタンダード』というのを発行しています。これは省エネプロジェクトか再生可能エネルギープロジェクトで、発展途上国の人達の生活に役立つプロジェクトであるという基準を満たしているプロジェクトに贈っています。それで今回のドイツ大会はその『ゴールド・スタンダード』の中からわざわざ選んでいるのです。それは、今回のドイツ大会と、次回の南アフリカ大会で行われるプロジェクト。そして津波で苦しんだインドのプロジェクトの3つです」